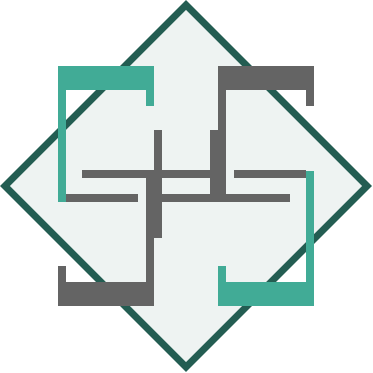令和7年度 年末調整:企業・従業員が押さえるべき最新動向
2025.10.31 更新
目次
令和7年度の年末調整は、税制改正により申告書の様式統合や控除制度の見直しが行われ、企業・従業員双方にとって実務対応の重要性が増しています。
特定親族特別控除の新設や基礎控除額の変動、住宅ローン控除の適用要件変更など、従来の対応では見落としが生じる可能性もあります。
本記事では、企業が備えるべき実務ポイントと従業員が活用できる控除制度の最新情報を、税理士の視点からわかりやすく解説します。
年末調整の基本的な意義と令和7年度の改正背景
年末調整は、給与所得者の所得税額を年末に確定させるための制度であり、企業が従業員に代わって所得税の過不足を調整する仕組みです。
給与所得者の多くは確定申告を行う必要がなく、企業が源泉徴収と年末調整を通じて納税義務を代行することで、税務行政の効率化と納税者の利便性が確保されています。
令和7年度(2025年分)の年末調整は、近年の物価上昇や少子高齢化、働き方の多様化を背景に、所得税法や租税特別措置法の改正が行われたことにより、従来の実務とは異なる対応が求められます。
特に、扶養控除や配偶者控除の見直し、住宅ローン控除の適用要件の変更、申告書様式の統合など、企業・従業員双方にとって影響の大きい改正が含まれています。
これらの改正は、税制の公平性と簡素化を目的としつつも、実務上の複雑化を招いており、正確な理解と対応が不可欠です。
企業側の実務対応と注意点
企業にとっての最大の変更点は、年末調整に使用する申告書の様式が統合されたことです。
これまで使用されていた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」「基礎控除申告書」の3種類が、「給与所得者の基礎控除申告書等(マル基・配・所・特)」として一本化されました。
これにより、記載項目が増加し、従業員への記入指導やチェック体制の強化が求められます。
また、基礎控除額が合計所得金額に応じて段階的に減額される制度(所得制限付き基礎控除)が導入されており、企業は従業員の所得見積額を正確に把握する必要があります。
たとえば、合計所得金額が2,400万円以下であれば基礎控除額は48万円ですが、2,400万円を超えると段階的に減額され、2,500万円を超えると控除は適用されません。
これに伴い、源泉徴収簿の記載方法や年末調整ソフトの設定変更も必要となります。
さらに、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)についても、令和7年度からは「年末調整での控除適用が可能な年数」が10年から13年に延長されたケースがある一方で、適用要件が厳格化され、借入金の使途や床面積要件、所得制限(合計所得金額2,000万円以下)などの確認が重要です。
企業は、該当者に対して「住宅借入金等特別控除申告書」および「年末残高証明書」の提出を促し、適切な控除処理を行う必要があります。
従業員側の留意点と控除制度の活用
従業員にとっての年末調整は、所得税の過不足を調整し、適切な控除を受けることで税負担を軽減できる重要な機会です。
令和7年度からは、扶養控除や配偶者控除の適用要件が一部見直され、特定扶養親族(16歳以上23歳未満の子)に対する控除額が引き上げられました。
これにより、大学生の子を持つ家庭などでは、従来よりも大きな控除を受けられる可能性があります。
また、配偶者控除・配偶者特別控除についても、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば38万円の控除が適用されますが、配偶者特別控除は合計所得金額が133万円未満まで段階的に適用されるため、パートタイム勤務などで収入が変動する家庭では、年末時点での収入見積もりが重要になります。
いわゆる「年収の壁」(103万円、106万円、130万円、150万円)に関する理解が不十分なまま申告を行うと、控除漏れや社会保険の加入義務発生など、思わぬ負担増につながる可能性があります。
さらに、生命保険料控除や地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など、各種所得控除の適用には、証明書類の提出が必須です。電子データでの提出が可能な保険会社も増えており、従業員は早めに証明書を確認し、提出期限を守ることが求められます。
特に、電子申告(e-Tax)やマイナポータル連携を活用することで、控除証明書の自動取得や申告書の自動入力が可能となり、利便性が向上しています。
だらだらと続けて説明いたしましたが、抑える要点としては下記の通りです。
特定扶養親族控除の拡充
16歳以上23歳未満の子(大学生など)に対する控除額が引き上げられ、税負担が軽減される可能性がある。
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば38万円の控除が適用される。配偶者特別控除は133万円未満まで段階的に適用。
「年収の壁」への理解と対応が必要
103万円・106万円・130万円・150万円などの収入基準を超えると、控除の適用外や社会保険加入義務が発生する可能性がある。
収入見積もりの精度が重要
控除額は所得に応じて変動するため、年末時点での収入見積もりが正確でないと控除漏れや過不足が生じる。
各種控除証明書の提出が必須
生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除などの適用には、証明書類の提出が必要。
改正による実務上の課題と税理士の役割
今回の税制改正は、制度の合理化と公平性の確保を目的としている一方で、実務上の煩雑さを増す結果ともなっています。
特に、申告書の統合により記載項目が増えたことで、従業員が記入ミスをするリスクが高まり、企業側のチェック体制が問われています。また、控除要件の細分化により、従業員の家族構成や収入状況を正確に把握する必要があり、従来の「一律対応」では不十分です。
このような状況下で、税理士の果たすべき役割はますます重要になっています。顧問先企業に対しては、改正内容の周知や実務対応の指導を行うとともに、従業員向けの説明会やQ&A資料の提供など、現場での混乱を防ぐ支援が求められます。
また、電子化対応が進む中で、クラウド型年末調整システムの導入支援や、マイナポータル連携の活用方法についてのアドバイスも有効です。
さらに、年末調整で対応できない控除(医療費控除、寄附金控除、雑損控除など)については、確定申告の必要性を従業員に周知し、必要に応じて申告支援を行うことも、税理士としての重要な役割です。
特に、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していない場合や、医療費が高額になった場合などは、確定申告による還付の可能性があるため、適切な案内が求められます。
まとめ
令和7年度の年末調整では、電子化の推進が一層進んでいます。
国税庁が提供する「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」や、マイナポータル連携による控除証明書の自動取得機能など、従業員の負担軽減と企業の事務効率化を目的としたツールが整備されています。
これにより、紙ベースでのやり取りを減らし、ミスの防止や保管コストの削減が期待されます。